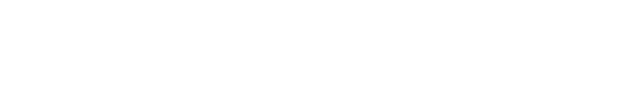益子焼3代目陶芸家に聴く!「今」に生きる文化継承の育み
山村:さて、今回の対談のお相手は、陶芸家の濱田友緒さんです。1967年に陶芸家、濱田庄司のお孫さんとして、益子町で誕生されました。その後、幼い頃から陶芸に親しまれ、多摩美術大学の彫刻科に入学、同大学、大学院をご卒業されました。その後は、今日まで、陶芸家として数多くの作品を生み出し、百貨店での展覧会出品も重ねていらっしゃいました。現在は、『公益財団法人濱田庄司記念益子参考館』の館長も務めていらっしゃいます。濱田さん、よろしくお願いいたします。
濱田:よろしくお願いします。
山村:きょうは、濱田庄司さんのお孫さんということもあったり、益子町で、大変、大きな窯元も構えてらっしゃるというようなところで、益子焼、それから、育った環境であるとか、これからやっていきたいこととか、そういったようなことをお伺いできればというふうに思うんですけれども。まず、濱田庄司さんのお孫さんということで、お生まれになって、お父さんとは、どんなお父さんだったんですか。
濱田:家族としては、10歳までは祖父の庄司と一緒でしたし、父はまだ、今、91で元気にやっております。ですから、最初の頃は、大きな三世帯住宅といいますか、立派な家でみんなで暮らしてる感じで、その中心に、祖父の庄司がいたという感じです。
山村:お父さんは、友緒さんにはどんなふうに関わってくれたんですか。
濱田:父自身が、苦労したといいますか、偉大な初代の下で比較されながら、プレッシャーを受けながらっていうところがあったので、私にはそういった重苦しさとか、プレッシャーを掛けないように、気を付けてくれていたような感じはあります。
山村:おじいちゃんである濱田庄司さんは、随分、お孫さんということで、かわいがってくださっていたんですか。
濱田:そうですね。自分自身も、粘土遊びしたりするのが子どもの頃から好きで、父や祖父がやってる仕事場にも興味があったので、呼ばれないでも、工房とか釜にちょろちょろ邪魔してたようなところがあって、祖父の場合は、「ちょっとおいで」って言って、「競争しよう、どっちが絵皿5枚、早く描けるかな」みたいな、遊びと、競争と、技術の習得を兼ねたような、競争しようって言いますと、大体、男の子は、やるぞってなるわけで、おじいちゃんに勝つぞっていって、勝って褒められるぞっていうような感覚で挑むわけですよね。
実際、本当に、庄司はそこで遊びながら自分の仕事を進めるわけですけども、私はそれを見ながら、自分ではこんなふうに描いてみようとか、おじいちゃんがこうやってるから、自分も近い絵でやってみようとか、子どもなりに考えながらやるとは思うんですが。競争するわけですけど、必ず勝つわけですよね。で、「負けた」って言って、子どもに、「大したもんだ、早いな」って言うと、おじいちゃんに勝ったぞってなるわけですけど、実際には、大人ですから、子どもが勝つように配慮して、スピードを緩めて様子を見てるんでしょうけど、ただ、勝つ、負けるじゃなくて、そこで内容を褒めるんです。この線は大人には描けないと。「こういう線、描いてみたいな」みたいに、褒めて、庄司は本当にそう思ってんのかもしれませんが、そういう形で、よく遊び感覚で、工房で陶芸の仕事になじんでた感じはありますね。
山村:お父さんのほうは、どんな感じなんですか。
濱田:やっぱり、自分の父親である庄司に踏襲した感じで、「じゃあ、おいで」って言って、「絵皿描いたらいい」って言うんですけども、与えられた絵付けの顔料が、薄い茶色と濃い茶色しかなくて、何となく子どもには渋いわけです。何しろってわけじゃなくて、用意してやったから、描きな、までなわけです。だから、晋作のほうは、ちょっと職人気質で、間違いのない絵筆を渡して、あまり散らからないような。
山村:どちらかというと、おじいちゃんのほうが芸術家で、お父さまのほうが技術的な職人肌っていうところがあったわけですか。
濱田:そう思いますね。
山村:当時も、お弟子さんとか職人の方っていうのは、たくさんいらしたんですか。
濱田:いました。にぎやかでしたね。
山村:そうすると、大勢の人が関わってくれるわけですよね。
濱田:そう思います。それ以外にも来客も多かったし、その中で、子どもがちょろちょろしてんのは職人から見ると邪魔なわけで、早く窯焼きしたいのに、子どもと遊ばれても困るんだよなみたいなふうに見てるように思うんですが、そういうふうな、職人たちの厳しいまなざしも感じながら過ごしてた思い出はありますね。
山村:小学校とか、中学校とかのときっていうのは、やっぱり、陶芸が自分の生活の中心だったんですか。
濱田:そんな感じがしましたね。仕事場が住居ですから、いつでも土の香りがする所にいた気はします。
山村:最初にろくろとかを触ったっていうのは、いつぐらいなんですか。
濱田:覚えてないんですが、小学校にも、ああいう焼物の里の小学校ですから、ろくろがあるんですよね、釜もあって。小学生のときには、それなりにろくろやってましたので、遊び感覚で覚えてたのかもしれないですね。
山村:その頃から素質は、他の子とは違ったようなところっていうのもあったんですか。
濱田:素質っていうよりは、図画工作とか、芸術面に関しては、向いてるなって思いはありました。
山村:そういう自覚が自分の中で。
濱田:そうですね。
山村:益子という、非常に、それこそ濱田庄司さんたちがつくられた陶芸の里なのかもしれないけど、そういった益子焼のようなものを、自分の中で意識するようになったっていうのは、いつぐらいなんですか。
濱田:とにかく、益子そのものが、私が子どもの頃っていうのは、非常に民芸運動が盛んで、日本中、世界中から注目を受けていて、その中心に濱田庄司がいるんだっていうことを、誇りには思ってましたね。その誇らしいおじいさんを眺めながら、自分もそこに憧れるっていうような思いがありましたね。
山村:それは、環境としては、一番いい環境ですよね。
濱田:そうですね、存在してることを感じてるわけですから。
山村:でも、その中にいる1人として、その偉大さとかに、プレッシャーとかっていうのは、全くなかったですか。
濱田:それは、先ほども話しましたが、父が、自分が苦労した分、周りに配慮したというか、プレッシャーを掛けないような配慮があったようにも思いますし、私自身も、いちいちそこでプレッシャー感じてるのももったいないといいますか、逆に、施設や、伝統や、素材が、十分にそろってる環境に、ありがたみを感じるっていうんですかね。突然、益子にやって来て、工房を造って、質のいい粘土や素材を作って、釉薬を開発して、釜を建ててっていう話は、ゼロからやることは大変で、それが、その一流の技術や材料が既にあって、そこに、しっかりとした技術を伝える人がたくさんいてっていう中にいることが幸せだなと、そういうふうに思いますし、それを生かさない手はないというか、生かさないともったいないじゃないかというふうに思ってますね。
山村:でも、思春期の頃って、自分のお父さんやおじいちゃんがやってることとは違うことをやってみたいとかって、そういう反発心のようなものっていうのはなかったんですか。
濱田:反発心はないんですが、美大に行ってるときに、どんどん自分の勉強してる内容がアカデミックな、技術的な、美術じゃなくって、現代アートとか、前衛アートに興味がいきまして、ついには、大学院の頃には、彫刻家として作品発表を銀座辺りの画廊でするわけですね。それも、作家デビューというのかどうかはよく分かりませんが、数回、自分の名前で陶芸展をする前に、現代彫刻展をしてます。
山村:なるほど。
濱田:その頃は、現代彫刻家と陶芸家の、二足のわらじもいけるんじゃないかとか思った時期もありましたが、いずれにしても、陶芸家をやめるっていう感覚じゃなかったですね。
山村:今、益子焼というものに関わっていらっしゃるわけだと思うんですけれども、濱田さんにとって、益子焼ってどういうものなんですか。
濱田:やっぱり、とても仕事がしやすい場所の窯業地だなと。一つは、伝統が浅いっていうんですかね、西日本を中心に、鎌倉期の頃から始まってる窯業地もあって、そういう所は伝統の重みがある分、自由さに展開できない部分があるんですが、益子焼は江戸後期から始まって、しかも益子焼としての理念があるわけではなく、商業的に、信楽焼や瀬戸の写しを作って、関東でも窯業をばんばんやろうというような、職人の民芸の里という流れから始まって。
近現代、民芸がちょっと細くなった頃に濱田庄司がやって来て、それが、90年ぐらい前で、その後、一気に芸術性を帯びた、個性豊かな益子焼が展開されると、そういった中でさらに、加守田章二さんとか、現代陶芸の方も次々と入ってきて、そういう足の軽いっていうか、自由なところがあって、そういう自由さが認められる場所っていうんですかね。その中で、私は三代目なわけで、三代目が老舗っていわれるぐらい伝統の軽やかな場所なんで、そういう自由さがベースにある、仕事のしやすさっていうのがありますかね。
山村:今から90年前とかっていうお話ですけれども、もう100年近いわけですよね。でも、三代目って言われると、確かに、まだ新しいって感じもするけれども、やっぱり100年続くっていうのはすごいことだなと思うんですよね。
濱田:そうですよね。
山村:この歴史をこれから先、濱田さんがどんなふうに伸ばしていこうっていうふうに思うんですか。
濱田:バブル期の頃の重厚長大な、そして高額な物っていうのがばんばん売れる時代じゃないので、やはり、親しみやすい品物や、価格帯の物に対する新しい益子焼で、また、従来とは違った、おしゃれな、デザイン的な部分も洗練された器作りなども考えなくちゃいけないだろうということがあって、益子町とも共同で、益子プロダクトという、デザイン開発組織をつくりまして、そこで、プロダクトデザイナーで、日本民芸館の館長もされている、深澤直人さんをデザインディレクターとしてお呼びして商品開発を行いました。これが、2年前から発足したもので、ローマ字で、『BOTE & SUTTO』というブランドで、新しい益子焼を、今、作っておりまして、私もそこに加わっているんですけれども、非常に、東京を中心に、好評なブランドです。
山村:デザイナーの方って、物事の考え方が、デザイン思考って、今、はやっているところがあって、問題とか課題を解決していくっていうような思考の仕方だと思うんですけども、濱田さんたちのような、感性とか、イメージを表現していく人たちとの間で、あまり、ぶつかるっていうことはないんですか。
濱田:やはり、民芸運動とか民芸も、いわゆる生活提案といいますか、その場所その場所のローカルな生活提案と、生活のための器を作るのが民芸だったわけで、それと、現代の生活の中で生かされていく、デザインの生活提案っていうのは、場所や、制作や、販売形態が違うんですが、基本的には、考えてることっていうのは、かつての民芸運動が提案した生活提案と、デザイナーの提案してる生活提案っていうのは、今、非常にフィットしてるんじゃないかと、そう思いますね。
山村:あまり異文化的な感じはないんですね。
濱田:そうですね。逆に、新しい感覚っていうのを次々と入れてきたのが益子焼なので。そういう意味では。
山村:そういう素地があるんですね。
濱田:民芸の産地に、濱田庄司の思想が入り、現代陶芸の思想が入りと、そういうふうにどんどんその場その場の、その時その時の、必要とされてる感覚や、形態が入ってくのが益子焼の良さでもあるので、そのまた新しい物事の積み重ねが益子の伝統となって、さまざまな色になって積み重なって、また益子の新しい色ができるという、そういうことだと思うので。
そのためには、どなたかが新たな提案をしたり、リードしたりする必要があって、それを、深澤直人さんのように、世界中を駆け巡って、世界中を動きを見てる人からの提案っていうと、やはり何か正しい、今後の進む道しるべみたいな感じのものを感じますね。
山村:具体的にどんな感じのものなんですか。
濱田:プロダクトデザイナーの方なので、洗練されたすっきりした物かと思ったら、「益子焼はやっぱり、ぼてっとしたのがいいね」って言うんですね。プロダクトデザイナーで、今までいろんなモダンな物を作られてたから、もっとシャープな、洗練されたものを提案されるのかと思ったら、益子はぼてっとしてるだろって、ちょっと、一瞬がっかりしたんですけど、やっぱり客観的に見たらそれが益子なんですよね。
ただ、そのぼてっとした器を全部並べたら、重たくて、暑苦しいから、すっとしたのも対比させようじゃないかという話をずっと打ち合わせでされてましたので、じゃあ、これをローマ字で商品化したらかっこいいかなと思って、私が『BOTE & SUTTO』っていう商品名にして、ブランド名にしませんかと。いいですねっていうことから始まったんですが、その、商品名、ブランド名と、その思想が全く同じ形でスタートしてるわけです。
山村:その中で、濱田さんも作品を作られているわけですよね。
濱田:私は、図面とデザインですかね。器の提案があって、こういう形でやりましょうかってところまでで、その図面ができた物を、うちの工房のスタッフが、それと同じように量産していくという。ただ、量産の仕方は、型とかそういった工場生産ではなくて、全部ハンドメイドのろくろで作ろうと、そこが一つのこだわりになってまして、いくら量産でも、手仕事の良さ、温もりは残そうということで、全部ろくろで作ることが、『BOTE & SUTTO』の魅力になってますね。
山村:それはいいですね。一つ一つ違うっていうことですよね。
濱田:作り手としては、寸分たがわぬ物ができてるはずなんですが、眺めると、やっぱり微妙に違うわけで、その並べたときの、独特の柔らかいゆらぎがそこに生まれるのが、深澤直人さんの狙いなのかもしれないし、そこで、型で作ったら非常に機械的な物が並んでしまって、冷たくなるところを、その指跡感っていうんですかね、それが見えるのが、一つの良い部分なのかなと思いますね。
山村:ちょっとこだわって聞きたいなと思うのは、今、一方で、社会的にAIであるとか、IOTであるとか、そういった技術の進展っていうのがすごく進んでいると。そういう中で、こういった陶芸のようなことに携わっている方って、イメージであったり、そのイメージを感じ取ることであったり、五感を使って感じ取っていく、それを表現につなげていくっていうところは、きっとAIにはできないところだと思うので、すごく、これから先、生きていく人にとって、示唆を与えられることが、とても多いんじゃないかなというふうに思ってまして、そういう中で、感じ取るために、何か、必要なことってありますか。
濱田:やはり、それは人の五感ですかね。触るとか、さっき言った、土の匂いとか、もちろん肥料の匂いとか、触った感触が柔らかい、冷たい、目で見るとか、そういった部分。AIっていうのは、それを数値化、データ化して分析するんでしょうけども、その分析にも入らないような、微妙な、細やかな感じ取り方、これは、個人差があるでしょうし、その人それぞれの人生もあるから、どう感じるかもあるでしょうし、好みもありますから分かりませんが。
体を使って、触ったり、見たり、匂いを嗅いだり、味わったり、そこにどのぐらい意識付けができるかっていうのが、その後の表現に進んでいくんじゃないかと思いますね。
人間は、動物は呼吸して生きてるわけですから、その呼吸をする感覚というのが、何にでも当てはまるし、機械には呼吸する物はないわけですから、やっぱり呼吸っていうのは、吸って吐いてですから、そのときにエネルギーを吸収する感覚があって、吐き出すっていうのは表現するってことでしょうから、作る側としても教える側としても、どう呼吸するかみたいな、呼吸に意志を持つっていうんですかね、そういう部分が必要かなと思いますね。
山村:先ほどもちょっと触れたんですけど、今の子どもたちって、ゲームであったりとか、こういったIOTの社会であったりとか、そういう所で生きていくわけですけれども、濱田さんのようなお仕事されている方から、何か子どもたちにメッセージを出すとしたら、どんなふうな内容のことがありますか。
濱田:昔やったことが全ていいんだよってわけでもないので、コンピューターが発達してたり、文明が発達してたりっていうものを、また生かしていくのも手でもありますけれども。やはり体感する感覚、触ったり、味わったり、時には痛い思いしたり。パソコンでクリック操作してても痛みもありませんので、ちょっとぐらいけがしても構いませんから、体当たりで何か突っ込んでってチャレンジするっていう、そういったエネルギーとエネルギーがぶつかるような、そういう場をたくさん体験してもいいんじゃないかなと。親御さんも含めて、ちょっとぐらいけがしていいじゃないかと。けがってどういうことなんだと、血が出たらどうなんだろうか、それも勉強なので、けがもしないように育てるっていうよりは、ちょっとぐらいけがしろよっていう、それでもいいんじゃないかなって。その上で、便利に使える物は使って、高速で進む物は使って、でも、ときどき、不器用なぐらい遅い作業もしてもいいんじゃないかな、みたいな。幅が広がったことはいいんじゃないでしょうかね。
山村:令和2年になって、新しい年を迎えたところですけれども、これから先、濱田さん自身が、ご自身に、何か育んでいきたいことっていうのは、どんなことがありますか。
濱田:作ることにおいて、健康であることっていうのも重要だと思います。体の健康や、精神の健康、これが傷んでると、やっぱり生まれるものも傷みますので、健やかさというのは、心身ともに健やかな身であるという、そこがまず大事なとこだなと思いますね。
山村:これから、まだまだ益子町を栄えさせていくまで、とっても大きな力になられるんだろうと思いますので、どうぞ、ご活躍をお祈りしています。きょうは、お忙しい中、お越しいただきましてありがとうございました。