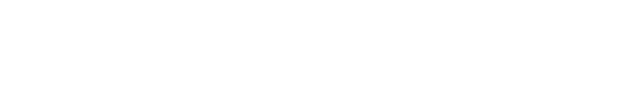レストランオーナーシェフに聴く!満足度を高める素材と言葉の育み
山村:さて、今回のゲストは、RESTAURANT chihiro、オーナーシェフの相馬千尋さんをお迎えしています。相馬さんは、宇都宮市ご出身で、大学では生物物理学を専攻されたということです。在学中にアルバイトがきっかけで、飲食業に興味を持ち、卒業後は市内のフランス料理店に就職。その後、軽井沢のフレンチレストラン、エルミタージュ・ドゥ・タムラオーナーの田村良雄さんに師事をし、2004年には料理長へ就任。2007年に完全予約制のフレンチRESTAURANT chihiroを、宇都宮市に開業されました。現在は、コンセプトの異なる店舗や、コンサルタント事業にも携わっていらっしゃるということです。それでは相馬さん、きょう、よろしくお願いいたします。
相馬:はい、よろしくお願いいたします。
山村:早速なんですけれども、飲食業界。このコロナ禍という問題でね、大変だったのかと思うんですけれども。そのあたりの状況、まず、お聞かせいただけますか。
相馬:そうですね。ある意味、飲食業界もそうですけれども、全てにおいて、結構、先が見えないっていうことや、このウイルス自体の正体も、いまだよく分からずっていうような部分もあるので。多分、きっとどの業界も、やっぱり先が見えないっていうことにおいての、今、いろんなことが決められないとか。多分、そういうところでのストレスのようなものがやっぱり、仕事をする側といいますか、サービスを提供する側であったり、それをされる側も含めて、なかなかストレスの強いものだったのかなというのが、本当に印象ですね。
山村:緊急事態宣言が出る前から、もう、休業的なところはあったんですか。
相馬:そうですね。でもやっぱり、緊急事態宣言において、で。そこから、ある意味では、県知事の発令。そういうところに合わせて、そのガイドラインに沿って、飲食業も含めですけど。そこで、それぞれの社内で、どのような対策を取っていくかという。ある意味、一つの、そのときには先が見える感じがあるじゃないですか。いわゆる、ある程度、やっていいことと、やっちゃいけないことがはっきりしてくる部分もあるので。そうなったときのほうがまだ、運営していく意味でのストレスっていうのは、少なかったかもしれないですね。決めやすくなったというか。何はともあれ。
山村:軸みたいなのが示されたからっていうことなのかな。
相馬:そうですね。それが分からないときは、結構、かなりお客さまにとっても。私たちにとっても、何が良くて、何が悪いのかという所が、手探りだったと思うので。余計に、スタンダードを、社会でも、お店でも作りにくいというか。そこは多分、共通した難しさだったと思いますし。やっぱり、社会環境が変化することで、業種的にも飲食業って、大体、先に影響が受ける、特徴だと思って。いいとか悪いとかよりっていうよりも、シンプルな特徴ですよね。なので、そういう意味では、やっぱり飲食業ってのは、先に。どばっと、影響を受けて。逆に言うと、そこに対して、どういうふうに対策を練ってくかっていう感じでしたね。
山村:なるほどね。このコロナの問題は特に、私も思ってることがあって。西洋の人たちに比べると、アジア系の人たちのほうが、感染者数が少ないのか、感染率が低いのかって。いずれにしても、比較をしてみると、アジア系の人たちは比較的、ウイルスに抵抗力があったのかもしれないんだけど。例えば、そういうことを、食文化のようなね、違いが、そこにあるのかどうかな、なんていうふうに思いながら、きょう来たんだけども。その辺、どうですかね。
相馬:そうですね。多分、私の場合は、さっきご紹介であったように、大学のときに生物物理学をやっていて。いわゆる、でも私もウイルス学は、最終的には専攻だったので。そのときの仲間は、今、本当に渦中にいるというのもあって。中途半端に、そこでの基礎知識が私にもあるというのも含めて。やっぱり、すごくその因果関係と相関関係の難しさというか。何がこうだからっていう部分がない。いわゆる、きっと多分、この文化的背景で、さまざまな、例えば。土足文化ではないとか、食文化の中でも、やっぱり、かなり日本て、食においては脂質が少ない文化なので。そういったものや、遺伝的なものとかっていう。場合によっては、例えば、疫学的にはBCGがどうのとか、いろんなお話が出てきた中で。やっぱりどれも、決定的ではないっていう、この難しさみたいな。
ただ、すごく思ったのは、やっぱり、経済の側面から見ると、とても疫学的には大変なことなんですけど、亡くなってる方とかもいらっしゃるので。経済的には、マーケットって必ず、常に変化してるじゃないですか。この変化しているマーケットのスピードが、やたら早かって、いわゆる、すごく震災とかと似ていて。マーケットの変化が早いというだけで、それ以外は、実は特に。大きなことではないんじゃなかろうかっていうのも、ちょっと考えていて。いわゆる、マーケットが、ものすごくスピード感を増して変化していったので。多分、飲食業にせよ、そうじゃない業種にせよ、何となく、短距離走が得意なマネージメントは、ある程度フィッティングできてるし。やっぱ、そうじゃない人たちは、こういう特殊な変化には。逆に言うと、得意不得意はあるにせよ、ただただマーケットが、ものすごくスピードで変化していったっていうことに対して。それでも世の中にとって、何が役に立てるのかというところを、サービスに転換していくっていうことは、必ずしも飲食店にとっては、全てにおいて難しいのかというと、そういう側面だけではないのかな。
山村:なるほどね。会社名も、imaginerでしたっけ。
相馬:はい。
山村:想像力とかっていう、イマジネーションから来ている。
相馬:まさに、そのとおり。
山村:のと一緒だと思うんだけれども。そういった意味で、今のようなお話を受けて。マーケットが、すごく早いスピードで変化をしていくと。で、相馬さんたちのような業界の人たちが、じゃあ、その変化に対して、これから先、どんなふうにしていこうとしているのか。あるいは、どんなふうに想像、まさにね。しているのか。そのあたりはどうですか。
相馬:今回、食っていう分野において見ると。何はともあれ、人は食べてかなくちゃいけないっていう部分において、これからさまざまな変化に対して、僕らは食を提供する側として、どういう方法で、サービスを提供していくかっていうところのフィッティングなんだと思うんですね。ビジネスという部分において。
そうなっていったときに、例えばですけど、今回、弊社で運営しているブランドの一つの、FARMDELIっていう、いわゆる、デリのお店ですね。どちらかというと、食べ物で体はできているような、そういったコンセプトでやっているので、健康志向のデリの専門店なんですけど。こちらは、イートインとテイクアウト、もともとやっていて。で、正直、売り上げの7割ぐらいがイートイン。3割ぐらいがテイクアウトだったというお店が、自粛によって、イートインがゼロになって。ただ、テイクアウトの3の部分は、かなり膨れ上がっているという現状があって。そこに対して、こっから先、シンプルに。仮にですけど、世の中が普通になっていっても、このテイクアウトの利便性っていうのは、ある意味、残るであろうっていう中でのイートインと。ってなってくると、逆にいうと、今までテイクアウトを経験しなかった人たちが、どばっと増えたことによって。例えば、その良さや、利便性を知って。で、そこのマーケットが大きくなると、逆に、普通の世の中に戻ったときに、イートインは元に戻ったけど、テイクアウトマーケットは戻りきらないはずなので。ある程度、増えた状態のまま、推移するよねってなってくると。もしかしたら、食全体の業界から考えると、マーケットって、大きくなったんじゃないっていう考え方にもなるじゃないですか。
山村:そうだね。
相馬:これ多分、どういうふうに世の中を見ながら、ある意味では、サービスとして、提供していけるのか。
それともう一つは、今回のコロナウイルスの件で、世の中の、食もそうですけど、全てにおいて。本音が見えたというか。いろんな人の本音が、ものすごく見えたと思うんですよ。会社一つとっても、それこそ、社長の本音、社員の本音だし。世の中だったら、食の分野においては、お客さまの本音。提供側の本音。で、そこの本音が見えたことによって、どこにサービスしなくちゃいけないのかっていうのは、ものすごくフォーカスされてると思うので。ここの本音っていうのは、丁寧に扱っていくことが、すごく重要なのかなっていう。
山村:その本音っていうのはね、例えば、どんなことに対してなんですか。
相馬:変な言い方ですけど、例えば、飲食店で、今まで行動が自粛されてないときであれば。自分の中で、行きたいお店が10個あれば。この10個を、仮にですけど、ぐるぐる回る。ただ、行動が自粛されたことによって、多分、3しか行けないと。その3のときには、上位の3に来るわけじゃないですか。そうなったときに、結果的には、マーケットの中で二極化が起こっていて。いわゆる、モテるお店ばっかりに、今度はみんなが行くと。10の行動から、3になったことによって、この3は、きれいに分配されず。いわゆる、みんなが行きたいお店に、ある程度、人が集中してしまうっていうことも起こっていて。てなってくると、変な言い方でいくけど、逆に、今回のこういうタイミングで、本来、増えてもよかったような飲食店であっても、あまりお客さまが増えなかった。多分これは、逆に言ってしまうと、これもお客さまの本音ですし。常連さんとして、ずっと通っていただいているお客さまが、こういうときだからっていって、そういった常連のお店から、テイクアウトを買ったりとか。そういうところから優先順位、思いも含めて。お客さまの行動っていうのが制限されたことによって、結果的にそれが、いわゆるマーケットの本音みたくなってきてる。
山村:もっと、乱暴な言い方なんだけど。なくてはいけない店と、なくてもいい店っていうのが分かれたってこと。
相馬:まさに、そうだと思います。これ、全てにおいてそうなのかなって気もしますし。一つの組織においても、それこそ、社員に対する社長の。どのようなかたちで、社員との接し方や、環境のつくり方っていうのもそうでしょうし。社員たちも、それに対する反応や、今後の自分たちの人生を考えたときの。やっぱり、お互い、さまざまな選択肢がある中で、選択肢が狭まれたことによって、本音みたいなものが、自然とあぶり出されてるような状況が。いろんな所で、いろんなさまざまな大小のコミュニティーの中で、行われてるなっていうのは、すごく感じますね。
山村:なるほどね。そもそも、どうして料理の道に進もうというふうに思ったんですか。
相馬:大学生のときに、小遣い稼ぎでやっていた飲食業のアルバイトがきっかけで。じわじわと料理が好きになったというよりは、気付いたら夢中になっていて。大学生の頃に、料理の本を買いあさるようになり。自分で、自然と掘り下げ始めたっていうのがきっかけですね。
山村:例えば、メニューをどうしようとか。そういったときって、どんなふうに考えていくんですか。
相馬:基本的には、すごく大切にしていることとして。もちろん、メニューも大切なんですけど。やっぱり、誰が、何をするかというか。何をするかっていうことよりも、誰が何をするのかっていうことが、すごく重要だと思っていて。で、この誰っていうのにあたる部分でいうと、私でいうと。例えば、これが、RESTAURANT chihiroというブランドであったり、FARMDELIというブランドであったり。パティスリーであったり、というかたちで。この、誰っていう部分を中心に、ものづくりをしていくんですね。いわゆる、コンセプトであったり、ブランドっていうものが、何をしたいのかっていうことを、丁寧に、考えながら、物を作っていくっていうことをするので。RESTAURANT chihiroであれば、おまかせのコースを提供していて。やっぱり、季節っていうものを、より感じていただけるような、お料理を提供したいなと思うので。やっぱり、今、ピークを迎えた食材から、インスピレーションを受けて、コースに仕立てていくっていう流れが多いですね。
山村:なるほど。そういった、思考の方法っていうのかな。
相馬:はい。
山村:そういうのって、どこで培われてきたっていうふうに思うんですか。例えば、誰かの影響がすごく、強かったとか。
相馬:もちろん、料理を作るにおいての技術的なものは、圧倒的に師匠から、いただいたものが多いですし。でも、どちらかというと、そこは多分、スキルのところなので。きっと多分、物を作るってなったときの、ゼロイチをやるときの、方法論ていうものが。今でもそうなんですけど、自分の中ですごく、当然、難しさというか。いわゆる、お客さまも、自分も納得したものを。納得して、私たちも作りたいし、お客さまにも、ある程度、受け止めていただきたいので。そうすると、きっと多分、自然と。何となく、本質的にといいますか。一歩一歩、積み上げていこうと思うと、自然と、誰っていう、さっき言ったような部分がものすごく重要で。そうすると、やっぱり、ブランドにせよ、人にせよ、誰の部分をまずは、きっちり明確に。というか、輪郭をつくっていくというか。そういうことを繰り返してるうちに、こんな感じになってっちゃいましたね。
山村:この前ね、お店にちょっと伺ったときに。カブでしたっけ? おっきな。
相馬:はい。ありましたね。
山村:例えば、あの場合、あの素材を使うというときに、誰がっていう点は。もちろん、RESTAURANT chihiroが、調理するわけだけど。でもその前に、作ってらっしゃる人もいるわけじゃんね。
相馬:そうですね。
山村:農家の方であったりとか。そういう方も、誰がに入るわけでしょ。
相馬:そうですね。ある意味、そういうのも入ってきますね。ただ、そこを誰がに、ある意味では、メインとして取り扱ってしまうと。誰がの部分が、ちょっと、がちゃがちゃしてしまうので。なので、基本的には、RESTAURANT chihiroとして、で、料理長である私が。最終的には、コースそのものを、季節の断面というようにイメージしてるんですけど。で、季節の断面のようなものが、もしあるならば、きょうのこの日の断面は、きっとこうであろうっていうのが、ある意味、コースの流れで。っていう所にフォーカスはしてるのですね。ですので、例えばですけど、今のおっしゃった流れだと、今年も多分、やると思うんです。去年もやったんですけど。親友の桃農家がいて。この桃農家の桃を使って、コースを仕立てるんです。全て。いわゆる桃の季節の断面を、提供するということですね。そのときには、主役はどちらかというと、私の中では、一気に生産者になるので。その生産者の思いであったりとか、その生産者の作った桃というもので、一つのコースを取り仕切って。で、私が料理は作るんですけど。その生産者を呼んで。で、徹底的に、その料理を召し上がってるお客さまに対して、その桃農家が、桃を語り尽くすわけです。
山村:なるほど。
相馬:そこに、さまざまな価値を付加していくというか。いわゆる、その桃を作った張本人が、お客さまからの素朴な疑問も含めて。いろんな、この桃の話をしながら、桃のコースをとにかく一晩、食べ尽くしてもらうと。前菜から、お魚、お肉、デザートまで、全部、桃で仕立てるので。なので、それは、先程おっしゃってたみたいに。生産者がフォーカスするってなると、そういうふうな、ちょっとした。RESTAURANT chihiroですけど、生産者との、いわゆる、コラボバージョンみたくなってくっていうようなかたちにしますかね。
山村:なるほどね。それも、面白いなと思うんだけど。よく、誰々さんが作ったものみたいなの出してるとこって、あるじゃないですか。
相馬:はい。
山村:あれも、すごく画期的だったなって、思ってはいるんだけど。確かにね、その生産者の方が、実際にお店に来て、食べてる所で、いろいろと講釈してくれるっていうのを聞くと。また一つ、利口になれるかなっていう気もするし。でも、この前から聞いてて、すごくいい言葉だなって思うのは、季節の断面っていう言葉。すごく、料理人らしい言葉だなとも思うんだけど。まず、でも、自分自身が、その断面に感じることっていうのがあるわけでしょ?
相馬:そうですね。
山村:例えば、今の時期だったら。今、何があれなのかな。今だとなんですか。
相馬:でも、さっき言ってた、桃もちょうど、はしりといいますかね。ちょうど出てきたところですし。で、その季節の断面っていうのは、僕の中で、旬という言葉に、似てはいるんですけど。この旬という言葉が、とても、ある意味、素晴らしい言葉なので。さまざまな、解釈があると思っていて。定義として。物量的に、一番ピークを旬なのか。おいしさの旬なのかとか。それこそ、はたまた、おいしさって、誰にとってのおいしさとか。ってなってくると、旬ていうのは、ある意味では、すごく素晴らしいんだけど、抽象的な使われ方なので。何か、それに変わる、季節を感じてもらえるような。何か、単語があったらいいなっていうので、多分、生まれてきた気がするんですよね。さっきの、季節の断面ていうのは。
山村:で、その季節の断面を、この前伺ったときは、お母さんが結構、説明してくださって。
相馬:そうですね。
山村:この店は、私で持ってるんだっていう感じだったけど。でもね、すごく一つ一つ、丁寧に説明してくださってて。ああいったことも、やっぱり、その日その日に、打ち合わせをして。こういうことをお話してね、とかっていうことを言ってるんですか。
相馬:そうですね。私がオープンのときに、お手伝いをしてもらえるようになって。それまで、母も、飲食業にいたっていうのもあって。自分で、小さなお店をやってたんですけど。タイミングもあったので。ちょうど、私が独立するタイミングで、予約制のフレンチというので。正直、私がそのとき28だったっていうのもあって。年齢が上の人が、お店に欲しかったっていうのも、正直あるんですよね。ブランディング的なことですよね。そこで、母に手伝っていただきながら。料理の説明なんかが始まって。お料理の説明に関してはやっぱり、それも最終的には、言葉そのものをどういう言葉を使うかによって、お客さまの感性を。いわゆる、お客さまが、ご自身で味わうわけですから。お客さまの感性を、引っ張りだす必要があるんですよね。ちょっと変な言い方ですけど、感じ方を誘導するというか。それに必要な言葉は、キーワードとして押さえてほしいと話はして。あとは、マダムの自分の言葉を使いながら。それぞれのお客さまに合わせて、説明をしているっていうところですかね。
山村:この前も、お話に出たんですけれども。何か、そういった季節の断面。今、思い出せないところもあるんだけど。テキスト化しないとか、言語化しないっていうような話、されたような気がするんだよね。
相馬:はい。
山村:あれ、どういう話だったっけ。
相馬:あれはですね、多分、自分の中でも。よく、けんかするんですよ。自分の頭の中で。いわゆる、料理と。じゃあこの料理に、このメニューの名前はなんですかみたいな。そうなったときに。いわゆる、料理を言葉で説明するっていうことの難しさというか。一つの。そこでよく、自分の中では、ある意味のけんかが起こるんですよね、きっと。言葉と、現実の料理とのずれというか。もちろん違うものだから、ずれはするんでしょうけど。きっと、もうちょっと、いいフィットするテキストや、言葉が見つかれば。また何か、腑に落ちる部分もあると思うんですけど。多分、当然、私から出てくるボキャブラリーじゃないですけど。それがやっぱ、伝わらないので。なかなかフィットできずに、いつも。どういう言葉で表現しようかというのは、悩みの一つですね。本当に。
山村:例えば、この前の、カブはカブであって。そこに、何か。感性を誘導する言葉っていうか、引き出していく言葉を。例えば、どんなことがあるんだろうな。よく、難しいネーミングになっている、レストランなんかでメニューを見ると。なんとかの、なんとかみたいなんあって。要するに、そういうことはしたくはないっていうことなんですか。
相馬:そうですね。ただ、料理の説明と、それこそ例えば、料理の写真があって。そこに対して、この料理名のタイトルは何ですか、みたいな。そういう話になると、大体、うちの場合には、一皿一皿に対してメインとなる食材が決まっているので。もう、その食材そのまま。例えば、カブの料理であれば、カブというようなものが、自然とタイトルになってくるような部分はあって。なので、一番最初にお出ししたサラダ。大体、あれでお花やハーブ入れると4、50種類は入ってるんですけど。あのサラダは、テーマが土というテーマでやっていて。それぐらいですかね。食材と、ちょっとテキストがずれてるのは。ただ、ある意味では、土を味わうといいますか。一つの。
山村:でもあれは、ドレッシングかなんかに、土が入ってるっておっしゃってたよね。
相馬:そうです。実際に、その野菜の採れた土からですね。香りや、ミネラルを抽出して。結局、一番、その野菜に合うソースって、そこが生まれてきた土かなみたいなところもあり。最終的には、土をテーマに作っていたというよりは、いわゆる農家さんたちの、今のたくさんの野菜をサラダに仕立てていった結果、イメージとしては、土のほうに寄ってったっていう感じではあるんですけど。そういうのがありますね。
なので、カブとかでいうと、例えばサービスとして。先程言ってたような、一つ、誘導する。テキストという意味では、例えばみずみずしさ。あのカブはやっぱり、すごくみずみずしさを感じる料理の一つだと思うんです。そこがいい所でもあり、料理としてはすごく、実は私としては、難しい部分もあるんです。みずみずしいっていうことによって、塩分のコントロールが、非常に難しくなるので。特に、カブの内側に塩分を入れようとすると。物理的には、水分が出てしまうので。実は、カブの中心には、塩分を入れられないという意味では、結局、水っぽい料理にもなるっていうことになってしまうと。これを多分、何も言わないで召し上がっていただくことによって、水っぽいって感じる人が出てくるんですけど。みずみずしさが売りの料理っていうことを、先に言うことによって。
山村:それが水っぽいんじゃないよってね。
相馬:じゃないよって、言えるわけじゃないですか。でも、それも多分、僕の中では、重要なことだと思っていて。分かりやすいところで言っちゃうと。そんなような、みずみずしさと、水っぽさって。ある意味では、物体としては水分量が変わらなければ、言葉の表現、どっちかってだけの話じゃないですか。そのときに、どっちがおいしいっていうところに着地させる意味では、水っぽいって表現のほうがフレッシュ感があっていいときと、みずみずしいのほうが着地するときがあると思うんですよね。
山村:もちろんそうだよね。
相馬:それを、ある意味での誘導。誘導というかね。やっぱりお客さまが、着地してほしい方向に、ちょこっと。コミュニケーションでいう、力学的にちょっと、そっちに押すというか。
山村:なるほど。
相馬:そんなようなことは多いですね。
山村:なるほど。光がある所に影があるっていうのと、影がある所に光があるっていうのと、一緒だよね。
相馬:まさにそうですね。
山村:で、どちらを取るかっていうね。
相馬:そうです。全く同じ量なんだけど、影側を見せたくないときに。光のほうに、フォーカスさせたり。あとは、その影がすごく重要なときには、あえて影側に、フォーカスを当てたいときもあるので。そのときに、いわゆる、感じてほしい苦味を、何も言わないと、すごく苦い料理で終わってしまうところを。すごく、甘みを生かすための苦味なんだっていうことを、先にきちんと伝えることで。お客さまも、効果を理解しながら、召し上がっていただけたりすると。結果的には、できるだけおいしくいただいてほしいっていうのがあるので。
山村:そうなんだよね。
相馬:その小さな一歩一歩なんですけどね。
山村:そうなんだよね。最終的には、この前もお話されてたように、おいしいって思ってほしいんだよね。
相馬:そうなんです。最終的にはやっぱり、おいしいって思っていただいて。
山村:ちょっと苦いなっていうのは、駄目なんだよね、だからね。
相馬:そうですね。本当に。最終的には、何かお客さまにとって、さまざまな期待を寄せて来ていただいているので。で、おいしいだけが満足感じゃないとは思うんですけど、でもやっぱり、せっかく来ていただいたら、満足して帰っていただきたい。その中の大きな要素の一つに、おいしさってあると思うので。極力、さまざまな方法で、ちょっとでも満足していただいて、お帰りいただきたいなと。その小さな一歩一歩みたいな感じですね。
山村:私もね、例えば高級の、非常にブランド力のある所に行って。おいしいものを、多分、出されてるんだろうと思うんだけれども。食べてみたら、率直にあまり、おいしくないなと思うんだけど。おいしくないって言えないで、もどかしさを持ちながら、お金を払って帰ってきた経験っていうのもあるとね。やっぱり、おいしかったって言って帰れるほうがいいからね。
相馬:そうですね。やっぱり。とは言え、料理でも、特に僕らがやってる、フランス料理の中でもイノベーティブって言われるような、ちょっと革新的な、現代的な表現をするようなジャンルだと、どうしても。おいしさだけが、最優先に来なくなってきてるというか。いわゆる、おいしさ以外の表現も、本当にさまざま出てきていて。お客さまも、おいしさにフォーカスしなくなってきてる方たちもたくさんいて。なので、これ、本当に多様化してきてるって意味で、すごく大切なことだと思っていて。ただ、あとは何を選ぶかは、そのシェフだったり、ブランドの価値観だと思うし。お客さまも、何をチョイスするかが、価値観だと思うんで。ただ本当に、うちの場合というのが、私の師匠がそうだったんですよね。師匠が、いわゆるそういうイノベーティブな料理というのが、好きな方だったんですけど。やっぱり、その師匠から新しい料理を作るたびに、常に言われたのが。それはうまいのかと。やっぱり、それはうまいのかというのが、僕の中でも価値観として大切で。どんなに当たり障っても、そのおいしいっていうところに、最後は着地させたいっていうのがあるんですよね。一つの、ものづくりとしてですね。やっぱり、これはいい悪いではなくて、価値観だと思うんですけど。
山村:そうだよね。イノベーションていう話になってくると、今までなかったものを作り出していくっていうことじゃないですか。すごく平たく言っちゃう話なんだけど。例えば、フランス料理で、イノベーションを起こしていくっていうときに。新しい味って、創造できるんですか。
相馬:そうですね。新しい味っていうのは。創造できるっていうのは、作り込んでいけるかっていう。
山村:そういう、自分の中で、例えば、新しい味にきっとなるだろうって。多分、思わないと、作っていけないと思うんだよね。でも・・・。
相馬:そうですね。
山村:結果として、新しい味になるのかどうか分からないけど。その辺はどうなのかなと思って、今、ちょっとね。
相馬:そこが、まず料理っていうもののくくりが、一言で言ってしまうと、表現になるので。先程の言葉だと、どちらかというと、新しい味もそうなんですけど、新しい表現ていうのが、多分イノベーティブって言われるジャンルで。これが、フランス料理の面白い所は、いわゆるそのジャンルがそもそも用意されているという。イノベーティブっていう文脈でいうと、絵画であったり、それはモダンダンスもそうですけど。モダンダンスやバレエも、そうだと思うんですけど。そういうかたちで、アーティスティックな部分に対して、イノベーティブのジャンルが、器がそこに最初から用意されている文化が、多分フランス料理の、一つの面白さというか。なんで、多分これを、何もない所で、日本とかでこういうことをすると、いわゆる創作料理みたいなところのカテゴライズに入ってくんですけど。フランス料理だと、最初から新しいチャレンジに対しての、器がある部分があるような部分があるので。そこはものすごく、フランス料理がすごい、さまざまな年代において、いろいろ新陳代謝しているような状況が環境としてできているのは。多分、フランス料理を面白いと思っている料理人の人たちの中に、多いと思うんですよね。そういう器があって、いろいろなさまざまな表現に対して、受け止めてもらえるようなマーケットがあったり、環境があったり。または、そっから選ばれるかどうかは、別だったりはするんですけど。
山村:私はね、この前伺ったときに、食べてみてというか。見てみてというか。フランス料理なの? って思ったんだよね。でも、私はすごく、自分の好みには合ってたと思うんだけれども。
相馬:ありがとうございます。
山村:でも、これをフランス料理って言っていいの? っていう感じもあったんだよね。でもそれって、すごく大事だなと、そのときに思いながら、帰ってきたんだけれども。その、日本人に好まれるというか。そういうようなところも、フランス料理の中に、文化みたいなのが融合してるような感じがして、すごく良かったんだけれども。その辺りは、何か思うことってあるんですか。
相馬:そうですね。本当に。逆に、フランス料理とは、みたいな。今度は話になっていくと。文化なので。今では、もう本当に、世界中でさまざまな人たちがフランス料理を作っているとこにおいて言うと、それ全体が。いわゆる、さまざまなことも含めてフランス料理の一部っていうふうになっていく解釈もあれば。やっぱり、例えば、逆に絞って。フランスで、フランス人が作るみたいな。そういうふうに定義付けをしていこうと思えば、できなくはないと思うんですけど。
山村:もちろん。そうだね。
相馬:ただ、多分、きっと料理って。きっと、そういうものではないんだろうなと。特に、ビジネスの分野になってくると。アーティストとして、一方的に発信するようなものを、ある意味では作っていって。その一方的な発信が、一つの美しさというか。正しさであれば、また、別の解釈ができるかもしれないですけど。やっぱり、例えばこの間だと。私が作った料理を、召し上がっていただいた、あのタイミングで、何となくですけど。変な言い方ですけど。その料理そのものが、私のものであり、お客さまのものでもあると、みたいな。二人称、三人称になってくみたいな。部分があるので。そういうところでいうと、多分きっと、もっと料理って自由なもので。本来は、カテゴリーっていうことでさえ、そもそも必要ないんだろうっていうのが、最終的な私の解釈で。
山村:持ち上げるわけではないんだけれども。あそこで食べさせていただいて、思ったのは、もしあれが。あれがって言っちゃ、失礼だけど。でもあれが、フランス料理だというのであるならば、多分、世界一のフランス料理の料理人だと思いますよ。相馬さんは。
相馬:とんでもない。
山村:いや、本当に。でもフランスに行って、フランス料理を食べて、もうおいしいかって言われれば、おいしくないときもあるからね。でも、すごく。やっぱり、食べる人への眼差しを持ってるのかなっていう気がしてね。帰ってきたんですけれども。きょう、時間がだいぶたっちゃったから、このぐらいにしようかな。きょうは、RESTAURANT chihiro、オーナーシェフの相馬千尋さんにお話を伺いました。相馬さん、ありがとうございました。
相馬:ありがとうございます。