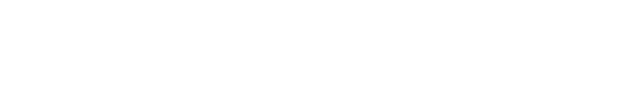専門用語集
教育保育・介護福祉分野では、たくさんの専門用語が使われています。ここでは、それぞれの用語の意味をわかりやすく解説。教育保育・介護福祉の理解を深め、サービス利用者や従事者のスムーズなコミュニケーションにお役立てください。
あ行
あ
アセスメント
支援前に対象者の状態や課題を把握するための評価作業。
アドボカシー
本人に代わって権利や希望を主張・擁護する活動。
アール・ブリュット
障がいのある人が生み出す独創的なアート作品。
アンガーマネジメント
怒りの感情を適切に理解し、対処する方法。
アウトリーチ支援
支援が届きにくい人に対して能動的に関わる支援。
い
意思決定支援
本人が自らの意志で選択・決定できるよう支える支援。
医療的ケア
たん吸引や経管栄養など、医療行為を伴う支援。
移動支援
外出が困難な人のための付き添いや交通の補助。
医療観察法
特定の精神障害者への医療と観察を定めた法律。
いのちの教育
命の大切さや尊さを学ぶ教育活動。
う
うつ病
気分の落ち込みや意欲の低下が続く精神疾患。
運動療育
身体を動かすことで発達を促す療育手法。
ウェルビーイング
身体的・精神的・社会的に満たされた状態。
雨天対応
屋外行事や療育活動での雨の日の代替支援策。
受け止め支援
利用者の感情や行動を否定せず受け入れる姿勢。
え
エンパワメント
本人の力を引き出し、主体性を尊重する支援。
エコマップ
本人と周囲の人・機関の関係性を視覚化した図。
エピソード記録
特定の出来事や支援を詳細に記録したもの。
エビデンスベース支援
科学的根拠に基づいた支援の実施。
エンゲージメント
利用者や家族との関係性の強さ・信頼度。
お
折り合い支援
本人の気持ちに配慮しながら現実と折り合いをつける支援。
オンライン面談
非対面で行う支援者と家族・本人との面談形式。
おたより帳
家庭と事業所間の連絡・情報共有の手段。
オープンダイアローグ
対話を通じて回復を支える精神ケア手法。
音楽療法
音楽を活用して感情表現や心身の安定を促す支援。
か行
か
環境調整
利用者にとって過ごしやすい空間を整える支援。
介護予防
高齢者の生活機能低下を防ぐための取り組み。
介護職員初任者研修
介護職としての基本知識・技術を学ぶ研修。
カンファレンス
多職種が集まり支援内容を検討する会議。
学びの保障
すべての子どもが適切な学習機会を得られるようにする施策。
き
危機介入
緊急的な状況下での迅速な支援対応。
基本動作訓練
立ち上がりや歩行など、生活に必要な動作の訓練。
記録(支援記録)
支援者が日々の関わりを残す業務のひとつ。
気になる行動
発達や環境に関係して見られる困りごとの兆候。
気持ちの翻訳
子どもの行動の裏にある感情を読み取り言語化すること。
く
クールダウン
興奮状態や混乱を落ち着ける支援。
グループワーク
複数人で協力しながら課題に取り組む活動。
クレーム対応
保護者や利用者の不満に対する適切な対応。
具体と抽象
学びのステップとして、体験(具体)から考察(抽象)へ導く支援。
車いす介助
安全で尊厳ある移動を実現するための支援技術。
け
ケース会議
関係者が集まり利用者の支援方法を検討する場。
経管栄養
口から食事ができない人への栄養補給方法。
健康観察
日々の体調を記録・把握する取り組み。
計画相談支援
福祉サービスの利用計画を立てる相談支援。
経験知
支援者自身の経験から得られた暗黙的な知識。
こ
個別支援計画
一人ひとりの目標やニーズに応じた支援計画。
コミュニケーション支援
言葉以外も含めた意思伝達を支える支援。
公的扶助
生活困窮者に対する制度的な支援(例:生活保護)。
合理的配慮
障害のある人が公平に暮らすための社会的対応。
行動観察
子どもの様子を見て支援のヒントを得る技法。
さ行
さ
サービス提供責任者
訪問介護などで支援計画を調整・管理する責任者。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
見守りなどのサービスが付いた高齢者住宅。
作業療法士(OT)
日常生活の回復を支援するリハビリ専門職。
サポートブック
支援が必要な子どもの特性や配慮点をまとめた資料。
し
支援員
福祉現場で利用者を直接サポートする職員。
支援学校
障害のある子どもに特化した特別支援教育を行う学校。
自己肯定感
自分の存在や行動を前向きにとらえる感情。
児童発達支援
未就学児を対象にした障害児通所支援事業。
す
ストレングス視点
本人の強みや資源に着目する支援アプローチ。
スーパービジョン
経験者が支援員に指導・助言を行う関係。
スケジュール提示
視覚的に流れを伝える支援方法。
数的理解支援
数の概念や計算に困難を抱える子への支援。
ストラクチャー化
支援場面の予測可能性を高めるための構造化。
せ
成長記録
子どもの発達や活動を定期的に記録するもの。
生活介護
障害の重い人に日中活動や生活支援を行うサービス。
生活リズム支援
起床・食事・活動などの生活習慣を整える支援。
精神保健福祉士(PSW)
精神障害者の生活を支える専門職。
そ
相互理解
支援者と利用者が互いの立場や思いを理解する関係づくり。
送迎支援
施設への通所時に安全に移動を支援する業務。
相談記録
面談内容や支援の流れを記録に残すこと。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)
対人関係能力を育てる訓練。
ソーシャルワーカー
社会的な課題に対応する福祉専門職の総称。
相談支援専門員
障害者の福祉サービス利用計画を立てる専門職。
た行
た
対人援助
人と関わる中で相手を支える支援全般。
体験活動
実際の経験を通して学ぶ活動(例:調理、買い物)。
他害行動
他人に対して攻撃的な言動や行動。支援の工夫が必要。
対話的支援
相互のやりとりを通して信頼関係を築く支援。
ターミナルケア
人生の最終段階に寄り添う心身のケア。
ち
地域包括支援センター
高齢者の生活支援や相談の拠点。
地域移行支援
施設から地域での生活に移るための支援。
チームアプローチ
多職種が連携して行う支援。
注意欠如多動症(ADHD)
不注意・多動・衝動性を特性とする発達障害。
地域密着型サービス
利用者が住み慣れた地域で受けられる福祉サービス。
つ
通所支援
日帰りで受ける福祉サービス(例:デイサービス)。
通級指導教室
通常学級に在籍しつつ、一部特別支援を受ける制度。
通知表支援
子どもの学校成績や所見を読み取り、支援に活かすこと。
通信支援
メールやチャットなどを使った遠隔支援の手法。
通院同行
病院への付き添いや手続き支援。
て
定期面談
保護者や利用者と定期的に行う話し合い。
提案型支援
本人の希望を尊重しつつ、よりよい方法を提案する支援。
デイサービス
日中に食事・入浴・機能訓練などを提供する介護サービス。
ティーチング
特定のスキルや知識を教える支援方法。
と
特別支援教育
障害のある子どもの個別ニーズに対応する教育。
透明性の確保
支援内容や運営情報を公開し、信頼を高めること。
動作観察
身体の使い方や習慣を見て課題や特徴を把握する技法。
トラウマ反応
過去の体験により心身に現れるストレス反応。
同意書
支援やサービスを受ける際の承諾を文書で確認するもの。
な行
な
ナラティブ
本人の語りを重視し、支援に活かすアプローチ。
内部研修
施設内で行う職員向けの学びや研修活動。
ナビゲーション支援
制度やサービスの選択を手助けする支援。
何気ない会話
日常的なやりとりから信頼関係を築く支援行動。
難病
治療が困難で長期の療養を必要とする疾患群。
に
日中活動
通所施設などで行う創作活動・レクリエーション等。
日常生活自立支援
身の回りのことを自分でできるよう促す支援。
入所施設
生活の場を提供する福祉施設。特養・障害者支援施設等。
入園・入学支援
就園・就学に向けた相談や準備の支援。
ぬ
抜け道支援
制度に当てはまらないケースへの柔軟な対応。
抜け防止チェック
記録や支援でのミス・漏れを防ぐ確認作業。
布絵本
発達支援や触覚刺激として使われる布製の絵本。
ヌードルテスト
感覚過敏を調べるための簡易感覚評価法(比喩的表現としても使われる)。
ね
ネグレクト
育児放棄など、必要な養育がなされない状態。
年間支援計画
1年間を見通して支援を計画する資料。
ネットワーク支援
関係機関・家族・地域とのつながりを活かした支援。
年齢相応支援
子どもの発達段階に合った支援内容の設定。
熱中症対策
夏場の体調管理や環境配慮の一環。
の
ノーマライゼーション
障害があっても分け隔てのない社会の実現を目指す考え方。
望ましい関係性
利用者と支援者の間に信頼と尊重を基盤にした関係。
農福連携
農業を通じた福祉活動や就労支援。
能動的支援
本人の意欲を引き出すことを重視した関わり。
ノウハウ共有
現場での知見や工夫をチームで共有する文化。
は行
は
発達障害
自閉症スペクトラム、ADHD、LDなどの総称。
配慮事項
本人の特性に応じて必要とされる環境・対応。
パーソンセンタード
本人中心の考えに基づく支援アプローチ。
ハラスメント対策
職場や施設内のいじめ・嫌がらせの防止措置。
ハンドオーバー
支援の引き継ぎや情報伝達のプロセス。
ひ
日々の記録
支援内容や本人の様子を記録し、情報共有するもの。
被虐待児支援
虐待を受けた子どもへの心理的・社会的支援。
非言語コミュニケーション
表情や動作など言葉以外の手段による意思表示。
ピアサポート
同じ立場の人同士による支え合い。
評価面談
職員の業務遂行や成長をフィードバックする面談。
ふ
福祉用具
生活支援のために使用される道具(例:手すり、歩行器)。
福利厚生
職員が働きやすくなるための制度(例:育休、研修支援)。
不登校支援
学校に通えない子どもへの居場所提供や学習支援。
服薬管理
服薬の履歴確認や飲み忘れ防止を支援すること。
文章支援
読む・書くことに困難を抱える人への支援。
へ
ペアレントトレーニング
保護者が子どもとの関わり方を学ぶ講座。
偏食支援
好き嫌いが激しい子への栄養・食事面の支援。
変化対応力
状況の変化に応じた柔軟な支援・対応力。
平等支援
公平性に加えて、それぞれに必要な支援を行う考え方。
ベースライン
支援前の状態(基準)を把握するためのデータ。
ほ
保護者支援
家庭への相談や不安の軽減を図る支援。
保育所等訪問支援
障害のある子が通う園等での専門的な支援。
包括的支援
多面的・全体的に支援する姿勢。
保育と療育の連携
教育・福祉両面から子どもを支える協働。
保健指導
健康的な生活を送るための情報提供や助言。
ま行
ま
マッチング支援
ニーズに合う支援先やサービスを紹介・調整する支援。
マニュアル整備
業務手順を標準化し、誰でもできる状態にすること。
まとめ書き
記録や報告などを1日の終わりに一括して行う手法。
巻き込み支援
本人・家族・地域など多くの人と関わりながら進める支援。
学びの振り返り
体験や支援の中で得たことを確認するプロセス。
み
見守り支援
干渉せず距離を保ちながら安全を確保する関わり方。
未就学児支援
幼児期の発達に合わせた療育や支援。
ミーティング
支援者間の情報共有や課題整理のための話し合い。
民間支援
行政以外の団体(NPO等)による支援活動。
む
向き合う支援
表面的ではなく深く関わる姿勢を持った支援。
無理のない支援
本人のペースや状態に配慮した支援計画。
無断欠席対応
事前連絡なしで休んだ利用者への対応と記録。
無償化制度
保育や通所支援の費用が免除・補助される制度。
め
メンタルケア
心の不調や疲れに配慮した支援。
明確な役割分担
支援者間での職務の整理と共有。
メモリーノート
本人の好みや特性を記した記録帳。
メール支援
文面を通じて行う相談や連絡支援。
も
モニタリング
計画通りに支援が進んでいるかを確認・見直しすること。
問題行動支援
行動の背景を理解し、望ましい行動を導く支援。
目的共有
支援チーム間で支援のゴールを一致させること。
モデル事業
実証的に行われる先進的な取り組み。
モバイル記録
タブレットやスマホを使った支援記録。
や行
や
役割基準書
職種ごとの業務内容と責任範囲を明確化した文書。
夜間支援
夜間帯にも必要なケアや見守りを行う支援体制。
ヤングケアラー
家族の世話を日常的に担う18歳未満の子ども。
優しい言葉かけ
本人の自尊心を傷つけない伝え方。
やりとりノート
家庭と施設のやりとりを記録する連絡帳。
ら行
ら
ライフステージ支援
人生の各段階に応じた継続的な支援。
ラポール
信頼関係のこと。支援の土台となる要素。
ライフレビュー
過去の出来事を振り返り、自己理解を深める支援。
ラーニングスタイル
その人が学びやすい方法・傾向。
ライセンス制度
公的資格・研修修了証など支援の質を担保する制度。
り
利用契約書
サービス利用時に交わす正式な契約書類。
リフレーミング
否定的な出来事を肯定的に捉え直す視点の転換。
リスクマネジメント
事故やトラブルを未然に防ぐ管理体制。
リワーク支援
休職からの復職を支援するリハビリ的プログラム。
臨床心理士
心理療法や発達支援に従事する民間資格者。
る
ルーティン支援
毎日繰り返す支援業務や作業。
類型分類
利用者の状態や特性に応じた区分。
ルールの明文化
支援方針や施設ルールを文書化すること。
ルーム環境整備
個別支援に適した空間を整える活動。
ルビ付き教材
読みやすさに配慮した教材や資料。
れ
連携支援
関係機関・家族・学校などとの協働。
連絡ノート
保護者との情報共有の手段。
レクリエーション
遊びや余暇活動を通じた支援。
レジリエンス
困難から立ち直る力。子どもや保護者支援でも重視される。
レスポンシブ保育
子どもの反応に応じて関わる柔軟な保育姿勢。
ろ
ロールプレイ
役割を演じながら実践的に学ぶ方法。
ローカルルール
施設や地域ごとの独自の取り決め。
ローテーション勤務
交代制による勤務体制。
ロングスパン支援
長期的視点での継続的支援。
ロービジョン支援
弱視者に対する視覚補助や情報支援。
わ行
わ
ワークショップ
体験や意見交換を通じて学ぶ参加型学習。
ワーキングメモリ
情報を一時的に保持しながら処理する能力。
わかりやすい説明
子どもや保護者に配慮した丁寧な伝え方。
わたし発信支援
本人の意見や希望を言葉や行動で伝えられるように支える。