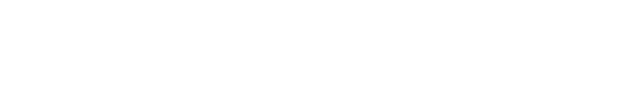業界基礎知識まとめ
法律や制度、新たな概念まで…教育保育・介護福祉、その他ギモンを、ジャンル別に専門家がやさしく紐解きます。正確な知識を身につけ、教育保育・介護福祉をより効果的にご活用ください。
あ行
あ
アイコンタクトの困難
目を合わせるのが苦手で、会話中も視線をそらしがち。
曖昧な表現の理解困難
「適当に」「ほどほどに」などの抽象的な言葉の意味を理解しにくい。
アスペルガー症候群
社会的コミュニケーションや対人関係の困難、こだわりの強さが特徴。
安心できる環境の重要性
変化を苦手とし、決まった環境やルーチンが安心感を与える。
い
異食症(いしょくしょう)
食べ物以外のもの(紙、布、土など)を口に入れる行動。
一斉指示が苦手
集団での指示に反応できず、個別の声掛けが必要になる。
インクルーシブ教育
障がいの有無に関係なく、すべての子どもが同じ場で学ぶ教育の考え方。
う
うつ伏せ寝の好み
体に圧を感じると安心するため、うつ伏せで寝たがることがある。
上手くいかないとパニック
計画通りにいかないと、感情が制御できず混乱することがある。
嬉しさの表現の違い
飛び跳ねたり手をひらひらさせたりと、独特な表現をすることがある。
運動協調障がい(DCD)
ボール投げやジャンプなどの動作がぎこちなく、運動が苦手。
え
絵カードの活用
口頭指示が苦手な子どもに、視覚的なサポートとして使うカード。
笑顔が少ない
表情が乏しく、感情を顔で表すことが苦手な場合がある。
エコラリア(反響言語)
他人の言葉をそのまま繰り返す(即時・遅延の2種類がある)。
枝分かれ思考の難しさ
「もし○○だったら?」という想像が難しく、柔軟な考え方が苦手。
絵本の活用
文字よりも視覚的に理解しやすいため、ストーリーを学ぶのに有効。
お
大きな声が苦手
突然の大声や大きな音に驚き、不安になりやすい。
オウム返し
会話の中で相手の言葉をそのまま繰り返す特徴。
音の反響に敏感
体育館や広い部屋などでの音の響きに過敏になりやすい。
音過敏
生活音や騒音が普通よりも大きく聞こえ、不快感を示す。
おもちゃへのこだわり
特定のおもちゃだけを好み、他のものには興味を示さないことがある。
か行
か
鏡文字を書く
「さ」「ち」「5」などを左右反転させて書くことがある。
過集中
興味のあることに没頭しすぎて、他のことに気が向かなくなる。
過敏性
触覚・聴覚・視覚などの刺激に敏感で、不快感を示すことがある。
仮面様顔貌(かめんようがんぼう)
表情の変化が乏しく、感情が分かりにくいことがある。
身体の使い方がぎこちない
ボールを投げる・階段を降りるなどの動作が苦手なことがある。
感覚過敏(味覚・嗅覚)
特定の食べ物の味や匂いに強く反応し、偏食につながることがある。
き
記憶の偏り
興味のある分野の記憶力が非常に高いが、日常生活の記憶は苦手。
聞き取りにくい話し方
声が小さい、早口すぎる、抑揚がないなどの特徴が見られる。
気持ちの切り替えが苦手
予定変更などに強いストレスを感じ、パニックになりやすい。
嗅覚過敏
生活の中の匂い(香水、食事、洗剤など)に敏感に反応し、強い不快感を示す。
興味の偏り
乗り物や特定のキャラクターなど、一つのことに強くこだわる。
緊張しやすい
環境の変化に敏感で、集団行動で極度に緊張することがある。
く
空間認識の困難
物との距離感がつかめず、ぶつかりやすかったり、字が枠からはみ出したりする。
クールな印象を持たれやすい
感情表現が乏しいため、冷たい印象を持たれることがある。
具体的な指示が必要
「ちゃんと」「しっかり」などの抽象的な指示では理解しにくい。
口の中の感覚過敏
歯磨きや特定の食感を嫌がることがある。
車や電車が好き
特定の乗り物に強い興味を持ち、詳しい知識を覚えやすい。
け
経験の一般化が困難
1つの場面で学んだことを他の場面で応用できないことがある。
計算が得意でも文章問題が苦手
計算はできるが、問題文の意味が理解しにくいことがある。
軽度知的障がい
知的発達に遅れがあり、学習や日常生活に支援が必要。
結果へのこだわり
自分の思った通りの結果でないと納得できず、やり直したがる。
けんかの仲裁が難しい
相手の気持ちを想像するのが苦手で、トラブルの仲裁ができない。
こ
好奇心旺盛
興味のある分野には強く惹かれ、深く探求することが多い。
行動のルーチン化
決まった手順を崩されると混乱しやすい。
興奮しやすい
好きなことに夢中になると、声が大きくなったり、動きが激しくなる。
言葉のオウム返し
質問に対してそのまま言葉を繰り返すことがある。
コミュニケーションの困難
相手の意図を読み取ることが苦手で、会話がかみ合わないことがある。
さ行
さ
作業のペースが極端
速すぎる or 遅すぎるなど、周囲とペースが合わない。
刺激を求める行動
体を揺らしたり、手をひらひらさせたりして刺激を求める
指示待ちになりやすい
自分で考えて行動するのが苦手で、指示を待つことが多い。
視線が合わない
目を合わせるのが苦手で、意図的にそらすことがある。
座っているのが苦手
長時間じっと座ることが難しく、体を動かしたがる。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
見守りや生活相談が受けられる高齢者向けの賃貸住宅。
サービス管理責任者
障害福祉サービスで個別支援計画を作成し、全体を統括する職種。
再発予防
精神障害などで再度の悪化を防ぐための支援。
作業療法
身体・精神の機能を回復・維持するための日常動作や創作活動を通じた療法。
佐藤式食事介助
利用者の尊厳を保ちながら食事をサポートする介助方法。
し
支援計画
利用者の目標達成に向けた支援の内容を記した計画書。
就労移行支援
一般就労を目指す障害者を対象とした福祉サービス。
児童発達支援
未就学児を対象にした発達支援事業。
施設入所支援
生活介護を受けながら施設に居住できる障害福祉サービス。
自立支援医療
精神障害・発達障害などの治療費を一部公費負担する制度。
す
ストレングスモデル
利用者の強みに着目して支援する考え方。
スーパービジョン
支援者が専門的指導を受けてスキルを高める仕組み。
障がい者スポーツ
障害のある人の身体的・精神的活性化を目的とした運動活動。
数値目標
業務や支援で設定される達成すべき定量的な目標。
スタッフ間連携
多職種やチーム内での円滑な情報共有と協働。
せ
生活介護
障害者に日常生活支援や創作的活動を提供するサービス。
成果指標(KPI)
サービスの質や目標達成度を可視化する数値。
成長支援
こどもや若者が能力を伸ばせるよう支える支援の枠組み。
セルフケア
自分自身の健康や生活を維持する能力・行動。
接遇研修
福祉現場での接客・マナーに関する学びの場。
そ
ソーシャルワーカー
社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職。
相談支援専門員
障害福祉サービスの利用計画を作成する専門職。
相互理解
支援者と利用者間でお互いの立場や考えを理解する姿勢。
卒業支援
療育や通所支援から次のステップへの移行支援。
総合支援法
障害者総合支援法の略。福祉サービスの根拠法のひとつ。
た行
た
対人関係の難しさ
相手の気持ちを察するのが苦手で、トラブルになりやすい。
多動傾向
じっとしていられず、常に動き回りたがる。
対人援助職
介護職や支援員など、人に寄り添いながら支える仕事全般。
多機能型事業所
複数の福祉サービス(例:児童発達支援+放課後等デイ)を1拠点で提供する施設。
退院後支援
精神科や病院から退院した人の地域生活を支援する取り組み。
対象児童し
サービスを利用する子どもやその保護者。
タイムスタディ
介護業務の時間分析手法。業務改善などに用いられる。
ち
地域支援事業
介護保険制度に基づき、市町村が提供する地域住民向け支援。
地域包括ケアシステム
高齢者が住み慣れた地域で最期まで暮らせる体制づくり。
地域移行支援
施設や病院から地域生活へ移行する人を支援する制度。
チーム支援
多職種や関係者が連携し合って支援にあたること。
注意欠如多動症(ADHD)
集中困難・衝動性・多動などが特性の神経発達症。
つ
通所介護
デイサービスとも呼ばれ、日帰りで介護支援を受けるサービス。
通知表支援
子どもの学校での成績・評価に基づく支援提案。
通園施設
障害のある子どもが通う発達支援を行う施設。
通知義務
福祉事業所が行政等に特定の事案を報告する義務。
連携通信(つうしん)
家族や関係機関との情報交換を目的とした通信手段。
て
定着支援
就職後に長く働き続けられるようサポートする制度。
定例会議
チーム間で支援内容や運営について確認し合う会議。
手話通訳
聴覚障害のある方とのコミュニケーション支援方法。
提供体制加算
介護保険サービスで、職員体制に応じた加算制度。
低所得世帯支援
経済的困難を抱える家庭に対する支援制度や取組み。
と
特定の音を怖がる
掃除機やトイレの流れる音などに強い恐怖を感じることがある。
独特な言い回し
難しい言葉や独自のフレーズを使うことがある。
突然の変化に弱い
予定の変更などにパニックを起こすことがある。
児童相談所
虐待や発達など子どもに関する相談を受け付ける公的機関。
特別支援学校
障害のある子どものための専門的教育機関。
特別養護老人ホーム
要介護者向けの入居型介護施設。
トラウマケア
心的外傷を抱えた人に対する心理的支援。
な行
な
泣きやすい
感情のコントロールが難しく、ちょっとしたことで泣いてしまう。
内部研修
事業所内で行う職員向けの教育・学びの場。
ナラティブ支援
本人の語りを尊重しながら行う個別支援アプローチ。
障害名(ナビゲーション)
支援を進める上で参考にされる診断名。
直ちに対応(ナグモ式など)
リスクマネジメントや事故対応での迅速行動。
に
においに敏感
柔軟剤や食べ物のにおいが強すぎると不快になる。
苦手な音がある
雷・花火・放送のチャイムなど、特定の音に強く反応する。
日中活動支援
就労・創作・生活など、日中に行う福祉サービス全般。
入所施設
生活をともにしながら支援を受ける居住型施設。
日本版ASD診断基準
自閉スペクトラム症を診断する日本独自の基準。
入門的就労
一般就労前のステップとしての就労訓練。
日中一時支援
一時的に利用者を預かることで家族を支えるサービス。
ぬ
抜け落ち支援(ぬけおちしえん)
制度や支援の網にかからない人への支援。
抜け(ぬけ)作業
支援計画や書類作成で起きやすい漏れ・確認不足。
抜き打ち監査
不定期に行われる行政等の立ち入り調査。
布の絵本(ぬのえほん)
視覚や触覚を使って学べる幼児向け教材。
ね
寝つきが悪い
夜なかなか眠れず、生活リズムが乱れやすい。
ネグレクト
育児放棄など、子どもの基本的欲求が満たされない状態。
年次評価
スタッフの年間の貢献や成長を確認する評価制度。
年間計画
事業所が1年間で取り組む支援・行事などのスケジュール。
熱中症対策
夏季における福祉施設での健康管理のひとつ。
ネットワーク支援
地域や関係機関との横断的な連携を図る取り組み。
の
ノーマライゼーション
障害があっても分け隔てのない社会を目指す考え。
農福連携
農業と福祉を組み合わせた就労支援の取り組み。
脳機能評価
発達や認知の特性を調べるためのアセスメント。
望ましい支援関係
信頼・尊重・対等性を重視した支援者と利用者の関係。
ノウハウ共有
現場での知見や工夫をスタッフ間で共有すること。
は行
は
話の脱線が多い
会話の流れを理解しにくく、突然違う話題を話し出すことがある。
パニックを起こしやすい
予期せぬ出来事に対して強いストレスを感じることがある。
場面緘黙(ばめんかんもく)
家では話せるが、学校など特定の場面で話せなくなる。
発達支援
子どもの成長や発達を促す多面的な支援。
配慮事項
支援対象者に対して特に気を配るべきポイント。
ハラスメント対策
職場内のいじめ・嫌がらせの予防と対応。
判断能力
支援や同意の必要性判断に影響する利用者の能力。
パート支援員
短時間勤務の支援スタッフ。多くの現場で活躍。
ひ
人混みが苦手
人が多い場所にいると疲れやすく、不安になりやすい。
表情が読みにくい
相手の感情を察するのが苦手で、適切な反応ができないことがある。
表出コミュニケーション
言葉・ジェスチャーなどで意図を表す行為。
非言語支援
視覚・聴覚以外のツールや方法で支援を行うこと。
被虐待児対応
虐待を受けた子どもへの心理的・社会的支援。
ひきこもり支援
社会とのつながりが薄い人への外出・自立支援。
ふ
不安になりやすい
小さなことで不安になり、過度に心配することがある。
福祉用具
介護・支援に活用される道具や設備(例:手すり、車いす)。
福利厚生
職員に対する報酬以外のサポート制度。
福祉教育
学校や地域での福祉についての学びの機会。
普通学級支援
障害のある児童が通常の学級で学ぶ際の支援。
不登校支援
学校に行きづらい子どもへの居場所づくりや相談支援。
へ
ペアレントトレーニング
保護者向けに子育てスキルを学ぶプログラム。
偏食対応
子どもの偏った食習慣に対する支援。
ヘルパー研修
訪問介護などを行う人向けの研修。
変化への対応
利用者の状況変化に合わせて柔軟に支援を調整する力。
ほ
放課後等デイサービス
就学児童を対象にした障害児通所支援サービス。
保育所等訪問支援
在籍先の保育園・幼稚園などでの支援サービス。
法定研修
事業所運営に義務付けられた職員研修(例:虐待防止研修)。
保護者支援
子育てや障害に悩む保護者に対する相談・支援。
保育と療育の連携
幼保と福祉が協働し、子どもを総合的に支える取り組み。
ま行
ま
マネジメント業務
施設運営や人材管理に関する業務。
マッチング支援
ニーズに合ったサービスや就労先との橋渡し。
巻き込み型支援
家族・地域・関係機関を巻き込んだ包括的な支援。
マニュアル整備
業務手順や緊急対応のための文書を用意すること。
み
見守り支援
利用者が安心して過ごせるような環境づくり。
未就学児支援
幼児期の発達支援を担う事業。
ミーティング記録
会議やケース検討の内容を記録すること。
民間支援団体
行政外で支援活動を行うNPOや社団法人など。
む
向き合う姿勢
支援者が相手の声や思いに真摯に応じる姿勢。
無資格者研修
未経験者や無資格者に対する基礎的な研修。
無理のない支援計画
利用者の状態や家庭状況に配慮した支援内容。
無断欠勤対応
スタッフや利用者の無断欠席への対応マニュアル。
無償化制度
幼児教育・保育・療育の費用負担を軽減する制度。
め
メンタルケア
支援者・利用者双方の心の健康を保つ支援。
明確な役割分担
スタッフ間での職務の棲み分け。
メモリーノート
利用者の生活歴や好みを書き留める個別資料。
面接技法
相談やカウンセリング時に用いる対話スキル。
目の動きの支援
視線入力や視覚認知に関する支援。
も
モニタリング
支援計画の進捗を定期的に確認する作業。
問題行動支援
不適切な行動への理解と対応を行う支援方法。
目的共有
支援チーム間でのゴールの一致。
目標設定
利用者の成長や自立に向けた支援の方向性を定める。
モデル事業
先進的・実験的に実施される取り組み。
文字支援
読み書きに困難のある子どもへの支援。
や行〜わ行
や
夜間支援
夜間にも見守りや介助を提供する支援体制。
役割基準書
職員の役割・業務範囲を明文化した資料。
ヤングケアラー支援
家族を支える子どもへの支援体制。
保育養護要録(やろく)
保育園等での子どもの記録帳票。
野外活動支援
キャンプや外遊びを通じた社会性・体験支援。
ゆ
有資格者配置
法定基準に従って配置される専門職(例:保育士、看護師)。
ユニバーサルデザイン
誰もが使いやすい配慮設計。
優先支援対象者
支援が特に必要と判断された利用者。
有機的連携
形式だけでなく中身のある本質的な連携。
ゆったり支援
過敏性や緊張が高い利用者へのペースを合わせた支援。
よ
予防的支援
困難を未然に防ぐための支援・取組み。
要介護認定
介護保険サービス利用に必要な認定制度。
読み書き支援
学習障害や発達特性を持つ子どもへの支援。
用具支給制度
介護・療育に必要な用具が補助される制度。
予後
今後の回復・発達の見通し。
ら
ライフステージ支援
年齢や発達段階に応じた継続的な支援。
ラポール形成
信頼関係を築く支援者と利用者の初期関係。
ライフレビュー
人生を振り返ることで自己肯定感を高める支援。
ラーニングスタイル
学び方の特性や傾向を把握する支援。
ライセンス制度
福祉業界での資格認定制度。
り
利用計画書
障害福祉サービス利用時に必要な個別支援計画。
リスクマネジメント
事故やトラブルの予防・対応。
利用者本位
利用者の意向を最優先に考える支援姿勢。
リハビリ支援
身体機能や生活能力の向上を目指す支援。
臨床心理士
心理療法や評価を行う国家資格に準ずる専門職。
る
ルーチン業務
日常的に行われる定型的な作業。
類型別支援
利用者のニーズ別に組み立てる支援体系。
ルール整備
現場での行動規範や手順を明文化する。
留意点
支援や運営で特に注意すべき事項。
ルーム環境支援
支援室や療育空間の整理・改善。
れ
連絡ノート
家庭との日々のやりとりに使う連絡手段。
連携会議
関係者が集まり支援内容を共有・検討する場。
レクリエーション支援
遊びや余暇活動を通じた関係づくり。
レジリエンス支援
困難を乗り越える力を育てる支援。
労務管理
スタッフの勤務状況や雇用環境を適切に管理する業務。
ろ
ロールプレイ研修
役割を演じながら学ぶ体験型研修。
ローテーション勤務
交代制の勤務体制。
ローカルルール
事業所独自の運営ルール。
ロジカル支援
合理的・構造的に組み立てられた支援計画。
ロービジョン支援
弱視者向けの支援や環境調整。
わ
ワークショップ
参加型で学ぶ研修・意見交換の場。
ワーキングメモリ
作業中に一時的に使う記憶領域。
和やかな関係づくり
支援者・利用者間の安心できる雰囲気の構築。
話し合い支援
本人・家族との丁寧な対話を重視した支援。
笑顔の支援
利用者の感情や安心に寄り添う対応を大切に。